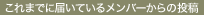

「知」に対する要求が強く (けい・兵庫・パートナー有)
(けい・兵庫・パートナー有)
4歳の息子は何事も積極的で、発達や学習に関しては何も苦労はないのですが、最近小学校に入るまでにどこまで教えていいのか考えてしまいます。数は「ビッグアバカス」を使い、いろいろな問題を自分で作って解いています。そうするうちに突然「足し算のノートが欲しい」と言ったので買い与えると、どんどん自分でやり始め、20までの足し算は簡単にできるようになりました。
最近は引き算を自発的に始めていますが、このまま本人の興味のままお勉強を進めていいのか考えてしまいます。わたしは普段、とくに勉強をすすめるようなことは何も言いません。もともとあまり早期教育には疑問があり、保育園に行っているだけで、お稽古もさせていません。生活やふんだんな外遊びの中でいろんな体験をして、そこからサイエンスにつながる知識を得てほしいと思います。しかし本人の沸き上がる「知」に対する要求がとても強く、数字はほんの一例で、文字や英語など知りたいことがいっぱいのようです。
不安にならないかと言われれば嘘に (たつぼう・東京・パートナー有・30代)
(たつぼう・東京・パートナー有・30代)
今1歳の息子がいます。幼児教育のパンフレットが多く送られてきますが、子どもが普通に暮らすなかで自分でいろいろ発見したり、経験したりして学んでほしいと思っているので、特別な「教材」を与えてはいません。ただ、「脳育」という言葉もあり、不安にならないかと言われれば嘘になります。なので質問に対する答えはYesにしました。でも他の方も書かれているように、学び方は十人十色。それに子育て方法の正解が一つなわけではない、と言い聞かせて、何とか自分なりに自信を持って子育てしていきたいと思っています。
「魔法のビデオ」のおそろしさ (aibe・大阪・パートナー有・28歳)
(aibe・大阪・パートナー有・28歳)
兄の子どもは、ごく小さいころからテレビ漬けで、幼稚園入園間近ですがほとんど会話ができず、「バイバイ」「ママ」程度です。両親子ども向けテレビ番組を録画したビデオでかけっぱなしにしており、子どもが大人しくなるので「魔法のビデオ」と呼んでいました。言葉の発達の遅れだけでなく、一時はやや異常と思われるほどヒステリックになっていた時期もありました。義姉が育児ノイローゼ気味で、同居している母たちにはまったく子どもに近寄らせないような状況だったので、周りから助けることもできませんでした。若い夫婦の子育て問題は本当に深刻です。テレビの弊害はもっと伝えなければ、知能だけでなく、心の発達がとても心配です。
子どものスピードに合った指導を(mamarin)
非常に難しい問題ですね。まず自分の子どもについて。長男(新5年生)は理解するまでに時間がかかるのですがいったん理解すると応用できるタイプです。ですから時間をかけてやればいいのですが、とりあえずこれを覚えなさい、覚えなければ次へ進めないというような項目を教えるのに苦労します。長女(新3年生)は逆にすぐになんでもとりあえず記憶し、先生の言うことを一言も漏れなく聞いているので、今まで学習に関して悩んだことがありません。
それから現在2歳から13歳までの子どもに英語を教えている教師の立場から言えば、本当に子どもの学びのスピードは千差万別で、能力もそれぞれすばらしいところがあると実感していますので、一人ひとりに覚えやすいように教える努力はしています。でも保護者の方は、やはりほかのお子さんと比較して不安になられているようです。親としてそれもわかるし、難しいです。
早いと気にならないが(ひろき&としきwithたかこ・兵庫・パートナー有・33歳)
4歳と2歳の息子がいます。上の子は、同じ年齢の子と比べて話したり、人とコミュニケーションをとったりするのは早かったと思います。逆に下の子は遅いほうでした。早いと気になりませんが、遅いのはとても気になります。しかし、昨春、上の子が入園した幼稚園は、とても個人を尊重してくれる園で、少し遅くても待ってくれるし、それをどうこう言われることもありません。この一年間それを見ていると、学び方や吸収のスピードの早い遅いは、どうでもいいのかな。と思う反面、やっぱり気になります。

興味のあることを自主的に学ぶ姿勢を(ocarina・東京・パートナー有・38歳)
以前どこかで読んだものに、「教育」とは、子どもの持って生まれた教えを育てることだとありました。本人が「教え」を持っているならば、大人は、それを上手に見守ることが最重要。学校の勉強にはついていってほしいけど、それ以外では、興味のあることを自主的に学ぶ姿勢をもってくるといいと思います。
教育改革にもっと力を入れてほしい(お気楽みわちゃん・岐阜・パートナー有・38歳)
入学前までは、早かろうが、遅かろうが、あまり親としても考えずに過ぎてくるが、学校という組織の中に入り、小学校高学年、中学となってくると、あ然とすることになる。私見としては、各々の能力の差があるのは、一人ひとりの顔や指紋が違うのと同様に、個性なのだから、認めてやりたいと思う。でも、まずは教育改革にもっと力を入れてほしい。人材も予算も。
その子のペースで向上できる環境を(あきんぼ・東京・パートナー無・37歳)
息子は、勉強はほかの子よりも先を進んでいるほうですが、運動能力、人付き合いは遅れているほうだと思います。でも、子どもを毎日じっくりと観察していると、少しずつですが成長していることを感じます。それに、このまま進んでいけば、自立するのに不自由がない程度にはなってくれそうです。だからまったく気にしていません。でも、学校のように一斉に同じことを学ぶ場にいると、習熟の遅い子は苦労するし、保護者は心配でしょう。早い子も遅い子も、その子のちょうどのレベルで、その子のペースで向上できる環境を与えてあげたいものですね。
何にも興味を示さない子どもであってほしくない(お江戸で小猿、トム吉!・東京・パートナー有・47歳)
わが家の一人娘の学習を目の当たりにしますと、少子化の弊害を痛感いたします。わたしも三人兄弟で育ちましたので、身の回りにお古でも教材が溢れていました。また学年は違っていても、勉強をしている子どもがすぐそばにいて、刺激を受けていたようです。学び方のスピードには不安を持ちませんが、何にも興味を示さない子どもであってほしくない、という危惧を抱きます。いくらコツコツと勉強を続けたとしても、興味もないことを覚えさせられる苦痛に耐えることに限度があります。いろいろなことに興味を持って、自発的に突き進む子に育ってほしい、と願っています。
多くの経験をさせてあげたい(MANAMI・東京・パートナー有・40歳)
基本的に早い時期から知識を習得させることには疑問を感じています。それよりも、いろいろな経験をして楽しんだり、何かに興味や関心を持ったり、不思議さを感じたりする心を育てたいと思っています。わが家は3人家族で、家族そろってお菓子などを食べるとき、息子がみんなに分けるということをしていました。ある時、5枚のおせんべいを3人で食べることになったのですが、息子はそれを見て、「あと1枚あると、1人2枚ずつ食べられるよ」と言いました。そうした経験があって、初めて、計算を学ぶことが生活の中で意味を持ってくるのだと思います。息子は、今、5歳ですがさまざまな遊びや生活を通し、多くの経験をさせてあげたいと思っています。
夫の思いつきに感謝(ありる)
初日のコメントを読んで、うなりました。じつは、4歳と2歳の女の子がいるのですが、4カ月ほど前に長女が夫に激しい口ごたえをしまして、その際夫から「そんな言葉を使うのはテレビの見過ぎだ! もう平日はテレビ見ちゃダメ! 土日も2時間まで!」と言い渡されたのです。それ以来、平日はテレビのコンセントを抜いている生活なのですが、まず格段に本を読む時間が増えました。また、ビデオが見られない分、絵本を与えて読んでやり、その後自分で繰り返し読み、いろいろと話し合いを楽しみ、土日にその話のビデオを見ると、ビデオをただ繰り返し見ていたときより、記憶が鮮明なようです。
また、本を読みながらだと、立ち止まって考える余裕があるようで、マネだけでなく、感想や質問がいろいろ出てくるようになりました。テレビだと、考えて反すうしている間もなく次の情報がどんどん入ってくるせいかな、と勝手に思っています。人とのかかわり、ただ与えられるのではなく、それに対して立ち止まって考える主体性を持ったかかわりというのは、テレビでは学びにくい種類のものなのかもしれません。今では夫の思いつきに感謝です。
「遅い、できない」とつねに不安があったが(きらら。・大阪・パートナー有・38歳)
子どもが幼いときは、よそと比べて「うちの子は遅い、できない」などとつねに不安がありました。しかし子育てにも慣れ、「なるようになる」と思うようになったら、気負いせず、楽になれました。子どもたちも小学校高学年になり、体力もつき、自分でできることの幅が広がると自信もついて、自分なりのペースで遊びも勉強もできるようになりました。
「ゆとり教育」で学習内容が難しいものが省かれたり、みんなで話し合う授業や自分たちが住んでいる地域の学習が増えて、学校教育も変わってきました。今は塾には通わせていませんが、もっと上を目指すには通わせたほうがいいのかな? 時代に取り残されるかもしれませんが、今は楽しんで学校に行っているので子どもまかせにしています。
大人が感性を磨くこと、子どもを見守る姿勢を(たまま・東京・パートナー無・38歳)
知識の多さ、人よりよくできることにこだわってはいけないと、自分に言い聞かせるようににしています。38年間生きてきて、ずば抜けて優秀な人はさておき、子どものころに輝いていたと見えていた人は、大人になるに連れ、失速していく人が多いように思うからです。7歳、5歳のわが子に一番大切なのは、自主性と自発力を育てることだと思ってます。勉強は「トレーニング」としてとても大切ですが、工作、お絵描き、空想遊び、ゲームの中にも、大切なものが詰まっているように思います。我慢してほっておいてあげる時間も子どもには重要でしょう。そしてやり遂げたことに関しては、子どもだましでなく、本気でほめること。不遜な言い方であることは承知ですが、子どものつくったものに関して、大人に見る目がなさ過ぎると思います。大人が感性を磨くこと、子どもを見守る姿勢をもつことが大切ではないかと思ってます。
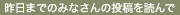
企業・官公庁がewomanリーダーズの声を求めています。一人ひとりの声をカタチにして、企業・官公庁に伝える。それがイー・ウーマンとewomanリーダーズの活動です。ぜひ登録を! 詳細と登録
詳細と登録

現在進行中のテーマはこれ! 今すぐご参加を!


 >>> 旧リーダーズ/メンバーからの移行登録について
>>> 旧リーダーズ/メンバーからの移行登録について
![]() 詳細と登録
詳細と登録