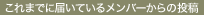

限りある資源、原発への不安(マリ)
なければないで何とか生活はできるものだと思っています。わたしは電気に限らず何でもそうして生きてきています。電気も同じだと思っています。限りある資源、原発への不安を考えると、今回のテーマについては支持します。
代替エネルギーの開発を(シンプル)
100%安全ということはありえないと思いますが、どの辺で「安全」と判断するかの線引きは非常に重要だと思います。事故が起こったときの人命、環境への影響を考えると、それと引き換えにしてまで便利さを追求しようとは思いません。代替エネルギーとして、より安全で、自然とも共存していけるようなものに開発の力を注いでいってほしいと思います。わたしたちは、これ以上の消費生活を望んでいるのでしょうか? もう一度考え直す必要があるように感じます。そういう意味で今回の判決を支持します。
便利さと効率ばかり優先するリスク(UML・北海道・既婚・40歳)
もんじゅの安全性についてはかなり不安を感じています。わたしは原発自体はなくてもいいと思っているくらいです。そのかわり生活が不便になっても仕方ないと。夜は暗いものだし、夏は暑いし冬は寒いのが当たり前。1年中過ごしやすいなんてぜいたくすぎると思います。命に関わるインフラ以外は不便で構わない。一度経験してしまった便利さはなかなか手放せないでしょうけど。地球に生かされている人間としてはこのままだと、とんでもないしっぺ返しをくらうような気がしてなりません。一刻もはやく安全でクリーンな電力を造れるようになってほしいものです。わたしはそれまでは不便でも我慢します。またこの分野の研究にもっと予算を使うべきだと思います。
国民一人ひとりがもっと学ばなければ(あるばーと・神奈川・既婚・36歳)
支持します。原子力というエネルギーを、人間という間違いを犯す可能性がある生物が制御できるのかどうか、疑問を持っているからです。石油に頼らず大量のエネルギーを得られる魅力的な錬金術ですが、偶然のミスが重なった場合に取り返しがつかない事態を招く可能性もあるわけです。多少のコストをかけてでも太陽光発電や水素発電(燃料電池)にシフトしていくことが将来のためだと考えます。根本的なところですが、裁判で決めることではないと感じます。行政が決めたり国会で議論して結論を出すのでもなく、国民投票などで直接判断すべきことだと考えます。そのためには、国民一人ひとりがもっと原子力のことについて学んでいく必要があるとも考えます。
今の行いが未来をつくる(しょうっち)
ここにも政治家と企業の癒着みたいのがみえかくれする。プルトニウムを使って、何らかの事故が起きたとき、どこが責任をとるのでしょう? 今じゃなく、「いつか」だからいいのでしょうか? 未来は今つくるものなのに、政治や企業のトップは今、しか見てないような気がしてなりません。でも、実際、電気は必要で、いっそうの節約は必要になるのではないでしょうか?
自己破産と同じこと?(sasayuri)
電気に頼る、頼らないの2択ではなく、限られた資源を再認識して、その中でいかに豊かな生活をおくるかを考えればいいと思います。便利だからと、自分の支払い能力を超えてキャッシングをして、破たんするのと同じでは?

国民も改善策を考えなければ(capital-one・埼玉)
こういったことを考えると本当に日本人の意識がぜいたくに慣れてしまい、そのありがたさが分からなくなってしまったと言えると思います。現実、われわれの街で電力が停止したらどうなるか。ライフラインがストップするのは当然ですが、知られざることで、あらゆるところのホストがストップします。そうすると日本で重要な場所の情報が回らなくなる。その先に東証が止まったら……。それだけで倒産するか給料を先送りするかを決断せねばならない企業は増えます。金融機関も支払えません。つまり、ライフラインは元より復活したときにわれわれの生活を維持することが不可能になります。たしかに自然には悪影響を及ぼしますが、文句を言うだけでなく、改善させられるだけのアイディアを作る義務が国民の側にあります。なぜなら、批判をしながらそのお世話になっているのは他ならぬ日本国民なのです。精神的な不安はいくらでも言えます。でもこれは対策を講じるまでは譲り合わないといけません。自前でライフラインと経済を維持できないんですから。
ウランを有効に使うことも必要(blueberry53)
今回の判決で一番寂しく思うのは裁判には、勝った負けたという判決になじまないものもあるのにと思ったことです。何が何でも原子力をなくしたい(もちろん、もんじゅもその一つ)という考えと、国策だからという主張、あるいは、事故は必ず放射能汚染につながるという意見と安全対策は十分であるという意見……多分絶対に相容れない部分があると思います。そして、それに判決を下し、勝者を決める……裁判はそんなものかもしれません。ただ、わたしは、もっと大局的に見れば、賛成、反対の両者をどうして歩み寄らせることはできなかったのかと思います。
現在のエネルギー、電力事情では、原子力は必要不可欠であり、将来燃料電池のような夢のエネルギーができても資源をまったく使わずに済ますことができないわけですから、ウランを有効に使うことも必要だと思います。また、軽水炉と違いナトリウムを使うということでより安全性を求められるわけですから、「安全」と言う前に、「危険だけど注意します」という姿勢で、もっと多くの人が納得できる対策や情報公開を進めることを国なども約束することが必要だと思います。今回、裁判所は、判決を出すのではなく、双方が話し合い、歩み寄ることを約束させる場にできなかったのかと残念に思います。「和解」……対立の構図から未来に向けて歩み寄る、そんなスタートの場にしていけたのではないかと思います。そして、そんな大局的な努力を裁判所もしてほしかったと思います。法の番人としては無理なことなのでしょうか。
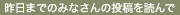
企業・官公庁がewomanリーダーズの声を求めています。一人ひとりの声をカタチにして、企業・官公庁に伝える。それがイー・ウーマンとewomanリーダーズの活動です。ぜひ登録を! 詳細と登録
詳細と登録

現在進行中のテーマはこれ! 今すぐご参加を!


 >>> 旧リーダーズ/メンバーからの移行登録について
>>> 旧リーダーズ/メンバーからの移行登録について
![]() 詳細と登録
詳細と登録