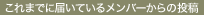

道の駅などで買えるようになり (ゆりぼたる・岩手・パートナー有・51歳)
(ゆりぼたる・岩手・パートナー有・51歳)
身近な食材をいち早く手に入れたいと思っても、どこで売っているのか、わかりづらかったのですが、このごろ道の駅などで、土地の農家の人たちが持ち寄った食材を手に入れられることがわかりました。すばらしいシステムだと思います。
すべてを地元外に出さなくても (てっしー・福岡・パートナー無・26歳)
(てっしー・福岡・パートナー無・26歳)
福岡は本来名物が多く、独特の習慣やイベントで「地産地消」を意識しなくてもたくさんの地元物を口にする機会があります。ただ逆に外に出てみると、わたしたちが旅行で求めている物はその土地の産物をその地で食すること。その場の空気が作用するということではないし、福岡にいても各地の産物は物産展などで入ってきますが、やはりわたしたちは現地に足を運んでしまうのです。少し観点がずれているかもしれませんが、けっしてすべてを地元外に出さなくても道はあるように思います。
地域の良さ発見の一助に (くろべえ・静岡・パートナー有・36歳)
(くろべえ・静岡・パートナー有・36歳)
地産地消について大枠で賛成です。新鮮さ、輸送の簡略化に伴う地球への優しさなど、さまざまな面でこの意識付けは有効だと思います。スーパーで並んでいる商品を見ても、ついつい地元産のものがおいしそうに見えるのはわたしだけではないと思います。わたしの実家は田舎なので、じゃがいもや大根、お米などは定例的に送ってくれます。実家あるいは近所の人が作っているものを食べると、不思議な安堵感があります。
地域には地域の良さが必ずあります。地産地消は、食の観点から、地域の良さ発見の一助になると考えます。ただ冒頭に「大枠で」と書きましたのは、基本的な食材を地産地消を意識し、各地域の産品なども折りをみて楽しみたいと感じたからです。人生を楽しむために、おいしいものを食べることは重要なウエイトを占めていると思います。旅行や記念日の際には、自分へのご褒美も兼ねていろいろなおいしいものを食べる、つまり、非日常的な範囲内においては、いろんな食材に挑戦していきたいと考えています。
故郷の経済に貢献したい(big5・東京・パートナー無・31歳)
わたしは、自分の生まれた土地で作られた作物が一番自分の体にいいと信じているので、多少値段が高くても故郷のものを買うようにしています。迷信かもしれませんが「鰯の頭も信心から」と言いますし、微力でも故郷の経済に貢献したいなと思っています。
「地のもの」が一番適している(しまこ・京都・パートナー有・37歳)
食材を購入するメインの自然食品店が、市内、府内の農家と契約を結び、省農薬・無農薬の食品を仕入れていますので、自然と地産地消を遂行していることになります。東京から京都に店舗を移したイタリアンのシェフも「京野菜は京都で料理するのが一番おいしい。それがわかってから、東京の店に京野菜を運ぶのをやめ、京都に店を移した」と雑誌のインタビューで話していました。やはりそこで暮らす人間には地のものが一番適しているのではないかと思います。
立場により「地産地消」がさまざまに解釈(kanamassaro・静岡・パートナー有・44歳)
わたしの住む静岡県は農業が盛んな地域です。お茶、みかん、メロンなど全国的に有名な産地であるばかりでなくさまざまな農産品が身近なところで生産されています。今朝、市内で最もにぎわっている食品スーパーに出掛けました。入り口の目立つコーナーに「地場野菜」と書かれたコーナーがあります。いかにも新鮮そうな静岡産の野菜がきれいに並んでいる中に鹿児島産や埼玉産など、他県産品がいっぱい並んでいました。このス−パーにとってここは「地産地消」をPRするところじゃなかったんだろうか? 「地産地消」「スローフード」など食を見直す動きが最近とても活発に見えます。でも、このスーパーがそうであるように、小売サイド、消費者サイド、行政サイド、マスメディアの「地産地消」に対するイメージがさまざまで、いま一つ効果的に浸透していないような気がします。今回をきっかけとして「地産地消」を考え直してみたいと思いました。
必ずしも安価ではないのが残念(アクアマリン・静岡・パートナー有・30歳)
「地産地消」ぜひ定着させていきたいものです。スーパーで買い物をする時も、地元産であることを意識します。「新鮮だし、輸送コストも少ないし」と思って。でも、必ずしも安価ではないのが残念なところです。わたしの住む静岡は、今の時期しらすが市場に流れるのですが、静岡県産のブランドなのでしょうか? 県外産よりも高いことが多いです。
生協にも入り(yumitaro・東京・パートナー有・35歳)
都内に住んでいるので、正直地産地消は環境的な問題から難しいと思います。公害や土壌を考えると、あまり地場物は消費したくないというのが心情です。しかし、考え方としては地産地消はとても大切だと思います。そこでわたしの場合、少しマクロにとらえて、関東近郊のものを中心に国産までなら地産地消だろうと考えて買い物をするようにしています。最近、地産地消をテーマの一つに掲げている生協にも入りました。なかなか元気のよい生鮮食品が届くので、見直しています。
地域のコミュニティーへと発展したら(ウッキーウッキー・パートナー有)
将来を担う子どもたちと考えることっていいですよね。小学校では、お米を授業で育てたり、農家などを見学したりしています。子どもの目から、自分たちの住んでいる地域の農産物を見て、新鮮な視点で意見を言ってもらうことも大切だと思います。
大人としては、これからの地域のあり方を考え、より地域に根付いた暮らしをするためには、ちょっと郊外に出掛けて行って、農家が軒先で販売している野菜や果物を買いながら、農家の人とお話ししてみる。地産地消という視点から、新しいコミュニケーションが生まれ、地域のコミュニティーが生まれたら楽しいですよね。
野菜は必ず「産直コーナー」で(rumik・愛知・パートナー有・34歳)
買い物に行くスーパー(JA関連)には「産直コーナー」が併設されていますので、野菜は必ず「産直コーナー」で購入します。新鮮で安いし、生産者名がラベルに入っているので、気に入ったら次も同じ人が作った野菜を買うことができます。新鮮な野菜が手に入るので、無駄にしてしまうこともなくなりました。

地元でしか消費しないのは、もったいない (潤・埼玉・パートナー無・34歳)
(潤・埼玉・パートナー無・34歳)
生まれ育った実家では、少し畑があるので野菜には困りません。地産地消はいいことですが、せっかくのおいしいものを地元でしか消費しないというのは、もったいないような気がします。おいしいものを、より多くの人に食べていただけるほうが、いいのではないでしょうか?
価格や今食べたいものという視点で選ぶと(asmic777・パートナー無・29歳)
特に意識はしていません。体のためには地産地消はいいとは思いますが、価格や今食べたいものという視点で選んでいくと、地産地消は難しいと感じます。関西から上京してきた時は、スーパーに並ぶ食材の違いに驚かされました。関西ではポピュラーな食材がなかったり、同じ名称で売られていても形状が違ったりということもありました。
小さいころから慣れ親しんでいる故郷の食材が売っていると、価格が高くてもついつい購入してしまいます。輸送手段が発達した現在だから可能な、ぜいたくなことだと感じています。長距離輸送による弊害もあるとは思いますが、故郷を離れて暮らしている人にとって、手軽に故郷の食材を楽しめる現在の状況はありがたいことなのではと感じています。
地元への愛着があってこそのもの(ちょこばなな・東京・パートナー有・30歳)
東京という土地柄のせいか、東京産の野菜は若干貧弱に見える上に値段が高いので、売られているのがわかっていても買うことはありません。そんなわたしでも、野菜やお米に出身地の「北海道産」という札がついていると、うれしくてつい手が出てしまいます。地産地消は地元への愛着があってこそのもの、と思いますので、将来北海道に帰ることになったら、地産地消で、ほかの地域よりも地元の野菜や乳製品、お肉を積極的に楽しみたいです!
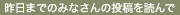
企業・官公庁がewomanリーダーズの声を求めています。一人ひとりの声をカタチにして、企業・官公庁に伝える。それがイー・ウーマンとewomanリーダーズの活動です。ぜひ登録を! 詳細と登録
詳細と登録

現在進行中のテーマはこれ! 今すぐご参加を!


 >>> 旧リーダーズ/メンバーからの移行登録について
>>> 旧リーダーズ/メンバーからの移行登録について
![]() 詳細と登録
詳細と登録