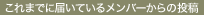

家だと断然表情が穏やか (utena)
(utena)
過去に営業でたくさんの老人施設に通ったことがあるのですが、感想は、施設によってあまりにも差が激しすぎる、ということです。そんなこともあり、多くの施設にはNoと感じてしまいます。
もちろん、自分が高齢になったら入りたいと思った施設もありますので、施設に入ることを親が選択した場合は、自分のしたい生活ができる施設だと判断してからにします。そして、同じように在宅ケアをされてる方の家にうかがったことがありますが、家だと施設にいる人よりも断然表情が穏やかな方が多いと感じます。
ただ、どれだけ訪問介護や訪問看護やデイケアなどを利用していたとしても、介護してる方の負担は否めないという現実も時折目にしました。ただ、子どもが介護するか施設が介護するかという選択肢だけでなく、一人暮らしで疾患を持っていても家で過ごせるシステムづくりが日本にもぜひほしいと思います。
90歳の高齢者のお子さんは70歳の高齢者なんですよね。そういうわたしには遠い話だけでなくても、現実的に遠く離れて暮らし、自分も夫も弟夫婦も仕事をしてることを考えると、なにかあったらイコール施設、という選択肢だけでは心細い気がするのです。
相手が身内のためヒステリックに(華姫)
身近に、身内の介護を受けている者がいます。相手が身内であることによって、介護を受けている者がヒステリックになることがあるようです。近い存在だからこそ、自分のやるせなさを見せたくないのでしょう。場合によっては、相手が他人のほうが楽に接することができる気がします。ただ、自分の親ですから、最終的に人の手を借りるしかない、という段階になるまでは、自分が面倒を見たいものです。

いつでも会いに行ける距離に (にーん・東京・未婚・33歳)
(にーん・東京・未婚・33歳)
わたしの母は、施設に入れてくれ、と言っています。高橋さんがおっしゃるように義父の世話を経験したからでしょうか。家の目の前の病院だったにもかかわらず、の意見です。娘たちが大変になることもあるのかもしれません。お金の面でも、そのために自分たちのお金を使ってほしいとも言っています。母の介護を見ているし、少しだけですが手伝ったりしていたので、わたしも施設に入れることに抵抗はありませんが、やはり入る側の親の気持ち次第ではないでしょうか? ただし、いつでも会いに行ける距離にいたいと思います。
多少の距離を置いた関係でいることも必要? (naomisan・東京・パートナー無・44歳)
(naomisan・東京・パートナー無・44歳)
わたしの父は盲人で加齢のせいか、最近難聴が進み、おまけに頻尿による軽度の尿漏れがあり、母が毎日キャンキャン言いながら世話をし、日々暮らしております。しかし二人とも80歳を優に超えておりますが、かくしゃくとしており、とくに父は光と音を遮断された中で軽度の物忘れは感じられますが、意志の強さをとても感じます。
しかしながら、わたしも軽度の障害を持っているため、体力的に親の介護をするのは大変な負担となるのは目に見えています。ですから日ごろから「何かあったら二人で仲良く施設行きだからね」と冗談とも本気ともつかないような感じですが言い聞かせています。わたしのように障害を持っているものや老老介護はお互いを不幸にします。また、親子といえどもあまり義務感にとらわれたり、自己をさらけ出すのではなく多少の距離を置いた関係でいることが核家族の多い現代に必要なのではないでしょうか?
心のケアは、家族がする(jskh・独身・29歳)
学生に社会福祉を教えています。肉体的、精神的にも、家族の介護負担を軽減できるため、抵抗はありません。介護のプロに任せるべきことはお願いし、家族だからこそできる心のケアは、家族がする、という考え方も必要になると思います。ただ、介護の質に関しては、大きな差があるのが現状です。きっとわたしは、何度も見学に行ったり、十分な説明を受けて、本人も家族も納得してから、入所を決めると思います。そうでなければ、大変ですが、居宅介護を選ぶかもしれません。
ストレスを溜めずにいいかも(プラス)
介護施設を選択することを考えるのはよっぽどの事態だと思うので、そうなると自分たちではパーフェクトな介護は無理でしょうし、それならプロに任せたほうが、親も自分もストレスを溜めずにいいんじゃないかと思います。介護施設に入れる=親を見捨てる、ではないと思います。
プロの世話になるのは安心(ジョゼフィーヌ)
現在、仕事で有料老人ホームや在宅介護サービスの広告をつくっているので、おのずと詳しくなってしまったのですが、選択肢の一つとしては、「あり」だと感じています。
介護期間が数年にも及ぶ場合や、その時の本人の状態によっては、いつでもプロの方のお世話になれる状態にいたほうが安心なこともあると思うので。しかし実際には、サービス内容やスタッフの対応など不安に思う面もあり、実際には自分の目で見極めて慎重に判断することが大切だと思います。
大切なのは入所する人の気持ち(jinglejungle)
介護施設に5日間研修で行ったことがあります。とても清潔で、設備も整い、穏やかな日々が送れる施設でした。このようなところであれば、両親を預けてもよいと思いました。しかし、入所している人との話を通じて、大切なのは介護施設の環境ではなく、入所する人(=親)の気持ちだと思います。介護できない状況にあって施設に入れるのは子どもですが、入所するのは両親です。強制的に入所させたり、入所後にぜんぜん会いに来なかったりするのは、問題です。両親が納得して入所しない限りは、どんなに恵まれた環境を整えた施設があっても、お互いハッピーではないと思います。
人に囲まれ生き生き(YUKI69)
抵抗はありません。今年亡くなった祖母が介護施設の短期入所を何度も利用していました。自宅ですることもなく、テレビを見続けている祖母よりも、友だちをたくさんつくり、介護のプロに見守られている祖母のほうが、生き生きとして見えたのは間違いありません。本人にとっても、また、預ける家族にとっても利用しやすい施設が増えることを願っています。
むしろポジティブな選択(live)
しゅうとが倒れ、介護が自分の問題となってきました。自分の仕事や活動はもとより、子どもにもいろいろな影響があるのが実際です。家族でという考えは、子世代の家族全体の生活に圧力がかかり、本人の了解があれば、施設の利用を選択したいものです。
施設に入れることは決して、責任放棄ではなく、介護を受ける本人にとっても、また介護を必要とする人を抱えた家族にとってもお互いがストレスをため込まず、生活を営むために、むしろポジティブな選択ではないでしょうか? ジェンダーに縛られた価値観もこれからは解放されていかなければ、共倒れの世の中になってしまうのではないでしょうか。
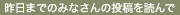
企業・官公庁がewomanリーダーズの声を求めています。一人ひとりの声をカタチにして、企業・官公庁に伝える。それがイー・ウーマンとewomanリーダーズの活動です。ぜひ登録を! 詳細と登録
詳細と登録

現在進行中のテーマはこれ! 今すぐご参加を!


 >>> 旧リーダーズ/メンバーからの移行登録について
>>> 旧リーダーズ/メンバーからの移行登録について
![]() 詳細と登録
詳細と登録