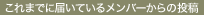

陪審制は…… (mikky108)
日本には以前から陪審制という制度は存在しており、現在は廃止しているのではなく、停止しているという状況ですよね。だいぶ前のことですけど。その頃の記録とか見てみたい気がします。日本人は単一民族ですから、アメリカなどと違い、民族の差別、偏見や利害対立などがないから、結構馴染むのではないかと、思いますが……。
被害者にとって理不尽なことが多いと思います。(ごまちゃん・横浜市)
薬害エイズの件、少年犯罪の件など、被害者にとってすごく理不尽だと感じる判決がたくさんあります。まだ判決はでていませんが、新潟の少女監禁事件では、9年間も監禁されていたのに犯人は最高でも10年の懲役にしかならないと新聞で読みました。奪われてしまった彼女の貴重な時間を考えると、納得いかない気持ちでいっぱいです。

事実から目を背けた判断
今日たまたま読んだ朝日新聞の特集で、幼児虐待をした親の裁判で証言する人が、世論や自分の感情に押されて事実と違う証言をしてしまうことがあると知りました。もし、陪審員(裁判員)になった人が、同じように感情や世論によって事実から目を背けた判断をするとしたら、とても危険な事態になると思いました。
真実を法廷で裁く限界(sinano)
民事と刑事の差はこの問題では大きいのでは?よくわかんないけど、最終的には人権を擁護しつつ、はたして裁判所という箱の中で事実を100%追求し、妥当な判決を出せるか?妥当な刑期は?現実に判断は一つではないはず。一般市民がそこに参加することは、どうしてかな?たぶん、人の考える善悪に近い判断になるからだろうね。法律上の基準ではなく。日本ではもう少しきちんと議論されるべきでは??
不透明な点が多すぎるので(きーす)
知り合いの弁護士さんに、昨今世間を騒がせた判決のいきさつについて、いろいろ聞きました。そうでもしないと、マスコミの偏りがちな報道に踊らされてしまうと思ったからです。わたしは実際に裁判の傍聴はしないので、新聞やテレビからしか判決の情報が入ってきません。しかも結果論のみが伝えられることの方が多いです。マスコミの報道は、報道する側の主観が必ず入っているとわたしは思うので、あくまでも情報源として考えて、真実は現場の方や判例を通して知るようにしています。いずれにしても、古すぎる日本の法律。現在の社会状況にあわせたものにしていただきたいです。
もっと議論を(わるわる)
裁判員の制度は、重大な刑事事件のみに適用されるということですが、どれが重大な事件でどれがそうでない事件なのでしょうか。被害者にとってはどれも重大な事件だと思います。あるいは、精神障害者が関わるような難しい事件に、一般の人が果たして正しい判断ができるのでしょうか。英国などでは、経済事件や医療事件など、高度に専門的な内容となる裁判については、裁判官ですら知識が不足しているのだから、陪審制度は馴染まないのではないかという議論もあります。この辺りのところがどうなるのかも含めて、裁判員の導入についてはもっともっと議論を持って練り上げた制度にする必要があると思います。
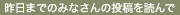
企業・官公庁がewomanリーダーズの声を求めています。一人ひとりの声をカタチにして、企業・官公庁に伝える。それがイー・ウーマンとewomanリーダーズの活動です。ぜひ登録を! 詳細と登録
詳細と登録

現在進行中のテーマはこれ! 今すぐご参加を!


 >>> 旧リーダーズ/メンバーからの移行登録について
>>> 旧リーダーズ/メンバーからの移行登録について
![]() 詳細と登録
詳細と登録