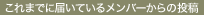

組織の利害と対決するためには(あけどん)
たとえば「医療過誤」などについては、専門領域に関する知識量の差の問題や、情報の非公開(守秘義務により保護されている)の問題があるせいか、とても一般人としては不利な裁判になっていると思います。まして背景に「利権」などドロドロしたものがあれば尚更です。「組織」は利害を共にしたとき強い結束を生み、悪い方向へと走り出すこともあるでしょう。その力に一市民が抗うには今の制度のままではかなり困難。裁判官の判決の履歴などもきちんと開示され注目されていくシステムを育てなくては……。犯罪(過ち)・弁護・審査・判決……すべて「人」の為す事ですから、「絶対」とか「完全」てありえないと思うのです。
医療関係や公的機関には甘いから(SacchanM)
薬害エイズの阿部被告が無罪判決を得たというのは納得できませんでしたね。この事件に象徴されるように、どうも医療関係の事件は医療関係者に甘いような気がします。それとお役人さんにも。こういった問題が解決できることを望みます。
被害者の「被害度」を見て!(yukipooh・海外・既婚・34歳)
始めに頭に浮かんだのは「非加熱製剤」の事件。危ないという情報はあったのに、そして実際にその結果HIV感染してしまった人たちがたくさんいる。それなのに、なぜ無罪?彼らの将来を奪ってしまったのに、なぜ罪に問われない?間接的な「殺人」もしくは「殺人未遂」と同じだと思う。これを見ると、日本も陪審員制度にして欲しいし、アメリカのように「1つの罪に対して1つの罰」にしてはどうだろう。例えば強盗殺人なら、強盗で懲役○ 年+殺人で懲役○ 年。加害者の人権を重視するよりも、被害者の受けてしまった「被害度」をしっかり見てほしい。
認知度・意識・知識に問題(京)
陪審員制度に似た制度が導入されるかも、というのは初めて知りました。最近、日本に陪審員制度があったらどうなるかという内容の、三谷幸喜脚本「12人の優しい日本人」という映画を観たのですが、あれ観る限りじゃ、日本に陪審員制度は向いてないですよね。もちろん、作品としてコミカルに書かれてるっていうのもあるでしょうけど。でも多くの日本人が優しいとかの以前に、他人事には無関心なんじゃないでしょうか。もちろん、こういう制度を取り入れることによって国民の意識も変わるかもしれないですけど、自分も含めて、裁判員制度に関する認知度は低いのでは。
先入観は怖い(lin)
薬害エイズなど「なぜ無罪?」って思う判決もあるけれど、逆に電車の痴漢とか、冤罪も多いって聞くと分からなくなってしまう。5人くらいに囲まれて「したんだろう」と脅され、「罰金払えば3日で返す」と言われて、した覚えのない痴漢の容疑を認めた友人がいます。もちろん痴漢やセクハラは絶対許せませんし、日本では刑罰が軽すぎると思います。でも、そんな風に間違われる人も被害者だと思います。一般人が司法制度に参加することによってこんな決め付けや先入観が入って来るとしたら、怖いと思います。
刑事罰と民事罰の違いわかってるかな……(Kikumi)
どんな裁判についても、国民全体が刑事罰と民事罰の違いを理解しているのかどうか、とても危ういと感じています。倫理社会などで習っているはずですが、どうしても感情論のみに走ったり、慣習やいわゆる常識のみに縛られているという印象がぬぐえません。わたしも個人でこのたび損害賠償で訴訟をする予定でたくさんの弁護士に面談しました。やはり自分の口から突いて出るものが感情論で、このへんをとても反省したものです。成文法からなる日本法が、陪審員制度という時代が変化するにつれて変化していく「モラル」というものとどのように折り合いをつけていくのか、楽しみではあります。
国民教育が先なのでは?(バル)
判決の結果を判断する上で、その判決を出した理由が重要であり、それによって判断が左右されるとわたしは考える。でも現時点で、これだけ情報産業が発達していながら、国民一般にその内容が充分理解できる程度に報道・教育がなされているとは感じられない。アメリカでは裁判の様子がテレビ放送されたり、学校教育の中にも取りいれられるなど、子どものうちから裁判が身近なものとして存在していると思う。そこまで日本国民に身近にしてくれる事を望むのは無理としても、今までは国民を司法制度というものから隔て、いわば過保護的状況に置いてきた、という事を充分理解した上で制度を整えてほしいと思う。急激に制度だけを変えることによって、無理が生じ、間違いを引き起こすというのでは、人の自由・生存に関わる事だけに、許されることではないと思う
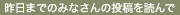
企業・官公庁がewomanリーダーズの声を求めています。一人ひとりの声をカタチにして、企業・官公庁に伝える。それがイー・ウーマンとewomanリーダーズの活動です。ぜひ登録を! 詳細と登録
詳細と登録

現在進行中のテーマはこれ! 今すぐご参加を!


 >>> 旧リーダーズ/メンバーからの移行登録について
>>> 旧リーダーズ/メンバーからの移行登録について
![]() 詳細と登録
詳細と登録