ホーム > news&policies > 「私の視点」 >
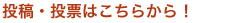
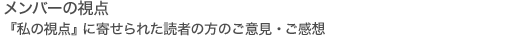
「個人」が救う株式市場(2003年3月15日)
日本版金融改革、というものがありましたよね。1996年に橋本首相の指示のもと、大蔵省がとりまとめた改革案です。2001年には日本の市場をニューヨーク、ロンドン並みの国際市場として再生するための案で、「1200兆円ものわが国個人貯蓄を十二分に活用して、経済の血液の流れを司る金融市場が、資源の最適配分というその本来果たすべき役割をフルに果たしていくことが必要。市場改革と不良債権処理とを車の両輪として進めていく必要がある」とし、改革の三原則を掲げました。三原則とは、“Free”“Fair”“Global”、すなわち「市場原理が働く自由な市場に」「透明で信頼できる市場に」「国際的で時代を先取りする市場に」。これを2001年までに遂行する、と書かれています。
さて、時は2003年3月。毎年のように、定例の3月の行事、株価対策が打たれました。監視を強めて、証券会社の自己部門による売買を管理する、「売り」を抑えるために、日本の生命保険、信託銀行に新規の株の貸し出しの自粛を要請する、減損会計を遅らせることを検討する、など、ビッグバンが聞いてあきれる項目のオンパレードです。まさに、改革の正反対、金融鎖国への道、を歩んでいるように思います。
今年も銀行は赤字決算です。今までに100兆円余りも不良債権処理で使ってきたからでしょうか。税金ももちろん投入されました。なのに、依然としてわたしたちは出口にはたどりつけていません。
わたしは、株も買っているし、損もしています。相場ですから、上がったり下がったりです。自律反発もあるでしょう。でも、日本の市場は、Freeでも、Fairでも、Globalでもありません。公的資金、といって年金資金を株に回す分を使って、今では死語になりましたが、PKO(Price Keep Operation)と呼ばれる株価対策も行われました。今度狙われるのは、個人資産だと思います。ただ、改革をせず、市場の需要サイドを盛り上げる対策も持たない、成長率マイナス1%の国の株は、本当に「買い」なのでしょうか。日本の東証一部の時価総額は230兆円です。中国の時価総額は、120兆円ぐらいだそうです。経済は年率8%で伸びています。永続するかどうかはわかりませんが、少なくとも、2008年ぐらいまでは、そのくらいのペースで伸びていくかもしれません。
日本の株価を本当に上げるにはどうすればいいか。いくつかあると思います。売り圧力を本気で抑えたいのなら、目先の対策としては、代行返上に伴う売りを、現金でなく、現物での返還を許せばいいのではないでしょうか。ですが、これは、株価を支えたい財務省と、年金を管轄している厚生労働省と、違う管轄なので、誰も手を付けられません。少なくとも、調整は難航します。ならば、あとは、やはり税金対策だと思います。所得と株式投資の損を通算できる、相続を株で行えば税率を下げるなど、もし本気で株価を上げたいのならリスクをとりやすくする方策を、検討する余地があると思います。そういう努力を惜しんで、小手先の株価対策ばかりに気をとられすぎているのではないでしょうか?
日本の市場を救うリスクマネーはどこにあるのでしょう。最近、外資の金融機関が日本からの撤退を表明しています。シティバンクグループは、日本を“watch list country”、つまり「経済成長が低迷し、将来リスクを抱える危険のある国々」のひとつに認定したそうです。その中にはアルゼンチンも含まれるとか。こうして、外資にも見限られたとき、日本のリスクマネーは、と考えると、もしかしたら、また「情」というのがキーワードになるのかもしれない、と思いました。今のネット証券とまったく逆の営業の発想ですが、老人国家に向かう日本で、毎日顔を見て、孫の話を聞いてくれる営業マン、彼にだったらお金を任せて、損しても構わない、という老人のお金。息の長いお金は、こういう形でしか出てこないのかな、と思いました。(はるたいママ)
藤田さんの考え方は、もっともだと思います。
ところで、お話のように、日本の企業の株価がこれまで何十年もの間、高すぎたのだとしたら、藤田さんは、あとどのくらい下がると、あるいはどのくらい上がると、実力相当のレベルになると考えていらっしゃるのですか。わたし自身は、株を購入した経験がなく、企業の業績や経済の実態が認識できていないのでさっぱり見当がつきません。
国あるいは日銀あたりが限界と思っているレベルと経済界が、投資家が考えているレベルと実際のところはほぼ同じなのでしょうか。バブル崩壊後の経済低迷がここまで長引き、今後もそれほど明るい展望が開けていないのであれば、理屈で考えれば個人投資家向けのアクションがもっと徹底して展開されてもおかしくないと思うのです。
国民全体の資産は1400兆円でも、実はごく少数の個人に偏っていて、そこそこのレベルの個人が保有する資産は、そのようなアクションの結果を期待できるほど体力がないのが実態ということではないのでしょうか。わたし個人の状況で言えば、とてもとても株の購入に回す資金はないので、残念ながらこの好機に投資するチャンスをつかめそうにありません。
専門家と目されている人たちの一致したアピールが繰り返されないようでは、「卵が先か鶏が先か」の話になってしまいますが、やはり企業の業績回復の実感か、新規企業の立ち上がりの活発化か、市民が期待できるような経済の動きが見えてこないと、投資に不慣れな個人は、新しく株を始めてみようという意欲が湧いてこないのではないでしょうか。(なつつばき)
- わたしは株を持っております。値下がりで塩漬け状態です。ただ、自己責任ですし、配当もありますので、我慢するしかないというところです。
- 個人の株式離れは、現在の市場環境の悪さと証券会社に対する不信感だと思います。
- 市場の信頼を損ねる企業行動(風説の流布、インサイダー取引、不適切な勧誘など)が個人の株式離れの根本にあると思います。
- 理屈どおりに動かぬのが株式市場というのが通り相場ですが、それはなぜでしょう。
- 公正な価格形成が行われ難いさまざまな要因があるのではないでしょうか。
- 会計制度、開示の在り方、日本版SEC(証券取引委員会)などの市場のインフラ整備も不十分です。
- 構造的な問題を飛ばして、個人の判断で、株を買うことを期待するのは、何かピンと来ません。
(A6M2)
関連情報
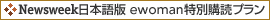


 >>> 旧リーダーズ/メンバーからの移行登録について
>>> 旧リーダーズ/メンバーからの移行登録について