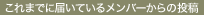

司法制度の理解を深め、意義ある議論を(mmmotoko・東京・パートナー有・37歳)
裁判員制度は、導入すべきだと思います。最終判決までの裁判制度・過程への意見、極刑に対する考え方など、いろいろな意見を持っています。が、司法に対する理解不足から無責任な意見が多いように思われます。立場が変わっても同じ意見を主張し続けることができるかというと、自信がありません。これでは、公平な審判はできません。制度の導入により、考える、学ぶ機会を得ることが大切です。ひいては、司法制度の改革につながっていくのではないでしょうか。司法についての素人が判決を下すというのは、非常に大きな問題があると考えますが、素人の意見を参考意見として取り入れられていくべきだと思います。アメリカの陪審員制度のように裁判員制度が機能するには、まだまだ時間を要しますが、肝心なのは、われわれがもう少し、司法制度の理解を深め、意義ある議論をできるようになることだと思います。
「定着させる」ことが重要(キョマリン)
どんな制度でもそうですが、「定着させる」ことが重要だと思います。制度をつくるだけでなく、それを機能させ、浸透させるためには、国の努力、そして裁判官の理解がこれまで以上に必要となってくるでしょう。個人的には、裁判員制度の導入により国民と司法との距離が縮まることを期待しています。
遺族の気持ちに配慮した判決ができる?(はるたいママ)
どの程度裁判員というのが判決に携われるのかわかりませんが、おそらく、今よりも被害者、または遺族の気持ちに少しは配慮された判決が出るのではないか、と思います。また、どのように重い犯罪であったとしても、判例からだけの判断で死刑にしてならないと思います。というのも、どの程度悪質かということで問われるといい、と思っていましたので。 過失致死だと最高刑が軽い、というのも、昨今見直されてはいますが、ケースごとにその悪質度を判断できるようにすれば、より人の心情に沿った司法ができると思います。

司法とわたしたちの間の架け橋に(Gengo)
裁判員制度が近い将来日本に導入されることを聞いてとても驚きました。この制度が導入されることにより、一般市民が裁判に参加するのだから、司法との距離は縮まるように思えます。しかし、本当に距離が縮まるのか疑問が残ります。司法に携わる弁護士または裁判官の中に、市民が入っていけるのでしょうか? 周りの人たちと同じ意見を持っていることに安心感を持つ日本人の国民性に、この制度をうまく浸透させることができるのでしょうか? 司法との距離が縮まるのではなく、司法との間に架け橋ができ、一般市民も渡ることができるような状態であると思います。
裁判員が災難に遭う可能性もあるのでは(ろくはる)
制度としては興味深いものだと思います。しかし、こういう考え方はいけないことなのだと思いますが、一般の人はそういう犯罪に「かかわりたくない」というのが正直なところではないでしょうか。仕事などの都合や被疑者の関係者とのその後の関係(暴力団やカルト教団系事件の場合)を考えると、それこそ裁判員に選ばれること自体が「災難」に遭うという位置付けになってしまうような気がします。日本の政府は何をやっても後手に回ってしまう現状を見ていても、裁判員に被害が及んでからその対応を考えるのではないか、そんな気がしています。
公正に人を裁くことなどできない(okochi)
アメリカの陪審員制度についての問題が書かれている書籍をつい最近読みました。『アメリカ人はバカなのか』(小林至著、ISBN:4-344-40340-1)。また、かなり昔の時代の出来事をテーマにしていますが、アカデミー賞を取った『シカゴ』でも、この陪審員の問題が扱われていますが、アメリカでも公正というわけではないようです。この制度が日本に導入されても、アメリカ同様公正に人を裁くなどということは絶対にできないでしょう。一番の理由を挙げるならば、日本人は人に影響されやすいです。特にメディアに毒されていてマイクを向けるとコメンテーターと同じような意見しかみんな言いません。他人の意見が自分の意見にいつの間にかなってしまっているケースですね。文章ではさまざまな意見が冷静に書くことができても発言する場において、一般市民が、本当に他人(有力者)の意見に耳をふさいでその事実の元に裁く能力があるかどうかは疑問です。
プリゼン上手の弁護士に騙される(さやたん)
アメリカで裁判を見た印象からすると、弁護士がいかにプリゼンテーションがうまいかということに騙されてしまう。ああいうのでは司法との距離が縮まるとは思えない。
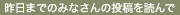
企業・官公庁がewomanリーダーズの声を求めています。一人ひとりの声をカタチにして、企業・官公庁に伝える。それがイー・ウーマンとewomanリーダーズの活動です。ぜひ登録を! 詳細と登録
詳細と登録

現在進行中のテーマはこれ! 今すぐご参加を!


 >>> 旧リーダーズ/メンバーからの移行登録について
>>> 旧リーダーズ/メンバーからの移行登録について
![]() 詳細と登録
詳細と登録