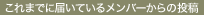

国立科学博物館へ連れて行った(yoshimi)
幼稚園の年中の子どもが「お友だちが化石を幼稚園に持ってきた」と言うので、上野の国立科学博物館へ行ってきました。まだ早いと思って連れて行ったのですが、彼は彼の年なりに、恐竜や宇宙へ思いをはせていたようです。帰ってからも「今日は楽しかったね」を連発していました。
まず褒めることからはじめている(akemimi・佐賀・既婚・33歳)
うちの子(男の子・6歳)は運動は苦手のようですが、工作や塗り絵、お絵描きは上手みたいなので、まず褒めることから始めています。そして、「お父さんは絵が上手、お母さんはお料理が上手、僕は何が上手かな? みんな一つは上手があるよ」とよく言って、得意なものを育てられるよう意識しています。
図書館の「絵本を作ろう」というイベントに参加(chokko・広島・既婚・31歳)
長女(6歳)はお絵描きと空想が大好きなので、図書館の「絵本を作ろう」というイベントに参加してみました。対象は小学生が主だったので心配しましたが、2時間を3日間集中してお話作りから下書き、清書まで一人でやらせました。わたしや主人は側にいただけ。興味があることだからこそ、こんなに集中できたのだと思います。
周りを見渡せば、「ここはこうしたら」とか「こうしないと」とか口を出す親御さんばかり、しまいには色塗りや絵にまで手を出す方までいました。お子さんは席を立って興味が薄れてしまったようでした。これを見て反面教師になったというか、「もっといいものにしてあげたい」という親の勝手な欲望に負けないように頑張りました。でき上がった作品は、子どもらしい今しか描けないものになったと思っています。
自分の常識を子どもに押し付ける教育はよくない(ののうさぎ・福岡・40歳)
わたしにはまだ子どもがいないので、このテーマに関する発言権はないかもしれませんが、周りの友人たちの子育てを見ていて感じたことがあります。友人の一人は、子どもが3人いて、お姑さんが子育てにかなり干渉してくるらしいのです。しかし、そのお姑さんは長年教育者として教鞭をとってきた方らしく、かくしゃくとして教え方も上手らしいのです。
しかし、幼稚園の子が、お絵描きで「ゾウさん」をピンクに塗っていたら、「ゾウさんはグレーでしょ」とすかさず訂正が入ったらしいのです。これが数学のように答えがはっきりしているものならいいのですが、お絵描きのように子どもの感性を育てるものの場合は、そういった教え方はどうかと思います。
大人は時に、自分の常識を子どもに押し付けた教育をしているのではないでしょうか。子どもは頭からダメをだされると、そこから先の伸びがなくなってしまうと思います。

子どもの興味を伸ばすのが下手(Cumin・大阪・独身・37歳)
わたしは、子どもの興味を伸ばすのが下手だと思います。たとえば、子どもが踊るのが好きだとすると、ダンス教室に通わせてあげよう!と思います。でも、子ども自身は何度も同じことを繰り返したり、先生に指導されたりする習い事が嫌いだといいます。そうすると、さて、どうすればいいのだろう?と考えてしまいます。
干渉かな?と思いつつもいろいろな刺激を与えている(mamarin・大阪・既婚・37歳)
とても難しい問題ですね。まさに「言うは易し行うは難し」です。現在10歳男児、8歳女児の親として、また、2歳から6年生までの男女児童に英語を教えている身としては、いろいろと考えさせられることばかりです。
自分の子に関していえば、長男は絵が大好きで、何にもしなくても伸び伸びとした絵を描きます。いくつかお絵描き教室のようなところにも通いましたが、本人の反応はいまひとつ。今夢中なのは、わたしの母が師事している高齢な日本画の先生。この先生の言うことなら何でも聞きますし、正座し何時間でも絵筆を握っているそうです(母からの伝え聞き)。それを思うと、わたしがしてあげられるのは、画材を買ってあげたり、描けた絵を褒めてあげたり、良質な展覧会に連れて行ってあげたりすることくらいなのです。
英語の生徒に関して言えば、とにかく彼らの一つ一つのレスポンスを集中して受け止め、真剣に反応してあげることくらいしかできません。
わたしの幼少期、親は多忙でほとんど放任でしたので、いろいろと興味があったことも見過ごされた感も否めません。わたしは音楽が大好きで、作文も得意でした。たしかに家に本はたくさんありましたし、音楽も満ち溢れていたのですが、それ以上の指導も与えてもらえたらと今になって思っているので、子どもたちには干渉かな?と思いつつもいろいろな刺激を与えている日々です。
親の不用意な発言はとても危険(nanachin・独身・27歳)
わたしはまだ子どもがいないのですが、わたしの体験。わたしは絵を描いたり物を作ったり、ということが極めて苦手なのですが、わたしの母はそういうのが得意。わたしがまだ幼稚園くらいのときに、わたしの絵を見て、「あんたほんとに才能ないねえ」と言ったのをいまだに覚えています。逆に、わたしの作文を読んだときは、「あんたはものを書く才能はあるね」と言ったのも覚えています。
その当時はそのことをあまり意識しなかったのですが、親の不用意な発言はとても危険だと思います。子どもにとって親の発言、親の存在は絶対的なもの。その親が「才能がない」と言ってしまえば、子どもはそれを認めざるを得ないでしょう。本当に才能があるかないかは、成長すればおのずからわかること。子どもが小さいときはとにかく褒めて、少しでもその子が興味を示したものに関するアイテム、情報をさりげなく提供するのがいいのかなあ、と思います。
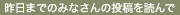
企業・官公庁がewomanリーダーズの声を求めています。一人ひとりの声をカタチにして、企業・官公庁に伝える。それがイー・ウーマンとewomanリーダーズの活動です。ぜひ登録を! 詳細と登録
詳細と登録

現在進行中のテーマはこれ! 今すぐご参加を!


 >>> 旧リーダーズ/メンバーからの移行登録について
>>> 旧リーダーズ/メンバーからの移行登録について
![]() 詳細と登録
詳細と登録