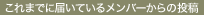

放任しておけない部分もある(kaho・既婚・36歳)
長男が幼稚園に入ったころは、何かと親が介入することが多かったと思います。気の弱いほうだったうちの子は、いわゆるやんちゃタイプの子が、遊びの延長で激しい行動をとることを嫌がり、泣いて登園を拒否したりもしました。子ども同士の付き合いは、親との付き合いにもつながってきますので、その辺りのストレスもかなりありました。次男の誕生や、年齢が上がるとともに、付き合い方(ゆずることや、我慢すること、意思を伝えることなど)を学んでいくんだな、と実感します。
小学生になって、親と少し距離ができた今、学校にも近所にも他学年の友だちができ、混ざりあった中から、学び取っている人間関係があります。しかしながら、判断力など、放任してはおけない危なっかしい部分も、まだまだありますね。
好き嫌いも選択のひとつ(osakasu)
6歳の長男の友だちが遊びにくると、必ず弟は仲間はずれ。4歳とはいえ一緒に遊びたいのですが、こればかりは子どもたちに任せています。「一緒に遊んであげてね」といっても遊ばないのはわかってますから。よそのお子さんも、気が合う同士が固まってしまい、全員で仲良く遊ぶことはあまりないですね。でも、仕方ないと思います。子どもにも好き嫌いはあるし、自分で決めていかないと。

クラスメートの把握も大事(mamarin)
自分が子どもだったころを思い出しても、親が友人関係に口出ししたことはありませんでした。それに、小、中学校の友人はその場が楽しいと感じる場合が多く、それほど深刻な付き合いではなかったので、自分の子どもにも口出ししません。ただ、普通でない事態、たとえば物や金銭のやりとりや、けがをさせられる、させたなどの事態が発生した場合にのみ介入すると思います。そういった事態が起こっていることに気づくためにはある程度クラスメートのことも知っておく必要があるでしょう。
企業・官公庁がewomanリーダーズの声を求めています。一人ひとりの声をカタチにして、企業・官公庁に伝える。それがイー・ウーマンとewomanリーダーズの活動です。ぜひ登録を! 詳細と登録
詳細と登録

現在進行中のテーマはこれ! 今すぐご参加を!


 >>> 旧リーダーズ/メンバーからの移行登録について
>>> 旧リーダーズ/メンバーからの移行登録について
![]() 詳細と登録
詳細と登録