ホーム > news&policies > 「私の視点」 >
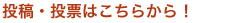
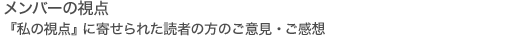
瀋陽事件の顛末 2002年5月25日
第二の中世
瀋陽の亡命事件、改めて考えてみれば不思議な事件です。
優秀なはずの外務官僚の、現実の危機を目の前にしての狼狽振り。亡命を希望する英文の書面が読めなかった、という言い分は、読めなかったのではなく、読む意思がなかった、と解釈するのが正確だ、と思います。
フランスの作家、マルグリット・デュラスの『ラホールの副領事』を髣髴とさせる、異様な無気力は、もしかしたら、もっと深い理由があるのではないか、と想像を逞しくせざるを得ません。
日本の、主としてエスタブリッシュメントの人たちが、亡命という行為や亡命者に冷淡なのは、自分が生まれ育った国や民族を捨てる、という選択に対する抑えがたい嫌悪感があるためではないか、亡命者を受け入れたら、余分な財政支出を強いられる、とか、治安が悪化する、といった現実的な不都合よりも、一つの家族や個人が、自分の国や民族や血縁の紐帯を断ち切って,自らの意思で国や政体を選択するという行為に、ただ単純に「我慢がならない」のではないか、と思えてなりません。
そこには、中国と北朝鮮との間の、あるいは、日本と中国との間の、外交的配慮といった近代的で明晰な政治的判断よりも、茫洋とした、多少はヒステリックな、東アジアに共通の、人間観、国家観の共同幻想が、より強く作用したように思えてならないのです。
そして、「何を、大袈裟なことを」と、おっしゃられるかもしれませんが、これが20世紀の左右のイデオロギー対立に取って代わって、政治・外交上の新しい対立軸になるように思えてならないのです。
個人の自由や自己責任を第一義に考える陣営と、国家や民族や血縁といった、暖かな大いなるものへの帰依を第一義に考える陣営と、世界は二分されて「第二の中世」が到来する予感さえあります。(守隨秀章)
公務員版「株主代表訴訟」はできないのか?
いつもコラムを楽しく拝見しています。今回の「瀋陽事件」をはじめとする、官僚たちの体たらくを見るにつけ、「株主代表訴訟の公務員版」ができないのかと思いました。
無能な経営者によって被害を被った株主が、その被害額の支払いを経営責任として求められるように、官僚にも納税者として被害の賠償を請求できるようにすれば、少しは自分の仕事や行動に責任感が出るのではないでしょうか?
と言っても、官僚も議員も裁判官も「公務員」な日本では無理なんでしょうかねぇー。(いまいくん)
関連情報
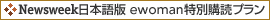


 >>> 旧リーダーズ/メンバーからの移行登録について
>>> 旧リーダーズ/メンバーからの移行登録について