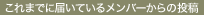

ブランコの危険(かず2038)
子どものころ、小学校に8個横並びになっているブランコがありました。順番は列を作って待つようにと先生に教えられていたので、左端に、みんなが列を作って待っていました。わたしの番になったときに、わたしから数えて、4台目のブランコが空きました。うれしくて急いで4台目まで走っていこうとしたときに、2台目のブランコが勢いよくわたしの頭に衝突。わたしはそのまま倒れて意識不明に。病院に運ばれ、何針か縫ったようですが、今でも縫いあとが残っています。今でもブランコは、人がいる公園で乗ることができません。
メーカーの対応に疑問(佐々木かをり)
娘が1歳のとき、保育園がトイレットトレーニングで使っていた「アヒルのおまる」で、股の部分を数センチ切り、出血をしたことがあります。子どもは、普通にまたがり、用を足しただけのようで、理由が不明。園では、担任の保育士さんは、あまりの出血でパニックして状況がわからず、メーカーの方は、園に呼ばれると、証拠物をすぐに持ち去ってしまいました。わたしのところに、メーカーの方が説明にいらしたのは、事故から何カ月もたった後。「おまるは、自宅で使うように作られていて、それも一人のためにあり、兄弟でも買い換えるべきものなので、保育園のようなところで、複数年使うものではない」「このような例はまったくない」という説明でした。わたしとしては、メーカーが、公立の保育園に販売したのでは?という大きな疑問もあり、他の説明も論理的でなく、その後このメーカーの商品の購入は控えています。
慣れ親しんだ遊具が消えるのは残念(エリザベス・愛知・既婚・40歳)
長男が1歳半のころ、ローラー滑り台から勢い余って飛び出し、頂上付近から落下したことがあります。その滑り台は、大型で幅広、左右の柵(手すり)がなく、ロラーが剥き出しだったため、斜めに飛び出してしまったのです。あわてて駆けより、抱きとめようとした夫の手にかろうじて当たり、ゆるやかに落下したため、鼻の下と唇を擦りむいた程度で済みました。もし直接落下して、激突していたらと思うとぞっとしました。その後、滑り台は落下防止柵が設置され、相変らず子どもたちの人気の遊具です。このように危険防止のための努力は必要ですが、最近よくあるような、使い方を誤ったために発生した事故のせいで、昔から慣れ親しんだ遊具が撤去されるのは、非常に残念です。
危険を察知する能力も身につけさせたい(巽・大阪・未婚・42歳)
子どもはいませんが、小学生がランドセルを背負ったままうんていに登って、はしごの間にランドセルがひっかかり宙吊りになって亡くなったといういたましい事故のニュースは記憶に新しいです。早く遊びたくて、ランドセルを外すわずかな時間も惜しかったその子の気持ちが想像できます。親の悲しみや、やりきれなさもまた想像に難くありませんが、誰も悪い人はいないという気もするのです。
遊具とは関係ありませんが、先日、流行りのロングマフラーがバイクのエンジンに巻きついて首が絞まり、重体となった女子学生。祭りの日に棒付きのお菓子をくわえたまま走って転び、棒が脳を損傷して亡くなった子ども。いずれも成長過程でその危険への察知を身に付けなければいけなかった事例と思います。子どもは擦りむいたり切ったりして危険を知っていくものだと思いますが、親だけでなく周囲の大人がその都度注意していくしかないですね。ポケットに手を入れて歩いていたら注意するとか、そういったことから。
大人が確認しておく問題(IDOBATAYA)
100%安全な遊具は、実際のところないと思います。ただし大人が、もっとそうした危ない点について、段階を追って子どもに教えることができているのか、好き勝手に遊ばしておいても遊具は、安全にできているものとか、まさかこんなことをしないだろうと、気配りしていないことのほうが責任がありませんか。また、そうした製作や設計をしているのも大人なのです。公共性や室内性とかも工夫なしに作られているのなら、子どもたちに与えさせたくないですね。

子どもは賢い(binko)
子どもには、「物や道具には、目的に応じて造られているので、その目的にそわない使い方をすれば凶器にもなる。だから、使い方を間違えないように」と教えているので、公園で遊んでいても羽目を外すようなことはなかったように思う。自己管理は自分で身につけるように教えたので、大きくなった今は何かと楽をしています。やっぱり、過保護も考えものだと思います。子どもは、大人の考えられない遊びを考え出して楽しんでますので、それをいちいち注意するよりも、根本的なものの考え方一つで、子どもは子どもなりに考えて行動します。子どもって賢いですよ。それを、うまく操るのが大人ですが、一つ間違うと、大人が操られる羽目になったらその子どもは、わがままに育つでしょう。
常に危険がともなうことを忘れない(belindy)
たまたま運が良かったのか、危険な目には遭ったことがありません。しかし、お友だちのお子さんが、滑り台の階段を登っている最中に手を離してしまい、後ろに転げ落ち頭部を縫うくらいのケガをされた話とか聞きました。他人事ではなく、いつも身近にその危険はある……と感じています。
ケガがないことがラッキーだった(ちっぽ・神奈川・42歳)
箱ブランコなど危険な遊具として取り外されている公園も多いですが、今までのところ、箱ブランコも含めて公園の遊具でヒヤリとするような経験をしたことはありません。男の子で、わたしもつきっきりで見ている親というわけではないのですが。ラッキーだったのかもしれませんね。
安全と危険を見分ける目(kimmy)
遊具のせいで子どもが危険な目にあうのではなく、遊具の正しい使い方を親がきちんと教えていなかったり、親同士がおしゃべりに夢中で子どもをきちんと監視していなかったりすることが理由なのではないですか? どんな物でも100%安全なものはないし、欠陥があるならそれは排除しなくてはいけないと思うけれど、昔からある物が、なぜ急に危険な物になってしまうのかとても不思議です。自分や子どもを見直すことも必要だと思います。今の子どもたちは安全と危険を見分ける目や体験がとても乏しいと思う。それは生きていく力にも影響してくるのではないでしょうか。
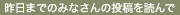
企業・官公庁がewomanリーダーズの声を求めています。一人ひとりの声をカタチにして、企業・官公庁に伝える。それがイー・ウーマンとewomanリーダーズの活動です。ぜひ登録を! 詳細と登録
詳細と登録

現在進行中のテーマはこれ! 今すぐご参加を!


 >>> 旧リーダーズ/メンバーからの移行登録について
>>> 旧リーダーズ/メンバーからの移行登録について
![]() 詳細と登録
詳細と登録