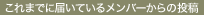

開かれることによって……(matyu・学生・既婚・24歳)
開かれた学校になって何が良いのだろうか?それは外から中を知ること、つまり子どもの様子がわかることだろう。そして子どもも外の様子が分かることも重要なポイントなのだと思う。つまり学校の中だけでは見えない社会や人とのつながりまでもが学校が開かれることによって子どもの五感で体験学習ができるのである。いつまでも鳥かごに入りきった環境の鳥が外へ飛び出せないように、いつでも外へ飛び出せる環境作りが今の学校には必要なことなのだと感じます。
閉ざしてしまう怖さもある(ladybird・東京・20代)
いくら鍵をかけて警備をしても、100%の安全なんてムリなんじゃないかと思います。学校の開放は、いろんな形で存在する学校内の暴力に対する抑止力でもあるはず。門を閉ざすことで、地域の目から隠されてしまうのは、とても怖いです。この事件に関する報道のやり方には、疑問を感じます。犯罪を未然に防ぐためという以上に、過激なことが言われているような……。
地域との共存を!(ふわりふわり)
核家族化が進んでいる今日、いろいろな人との交わりを体験できる場所として、開かれているべきだと思います。既に老人会との交流をしたり、学年を超えて活動したりと試みているところはあります。今までは、「開かれている」ということばかりに気をとられて、「安全」がなおざりになっていたのではないでしょうか。これは学校という施設に限らず、日本の社会全体に言えること。このところ政府にもやっと「危機管理」なるものが芽生えてきたんですものね。「開放」と「安全」を両立するために、「地域の目」が果たす役割がでてくるのではないでしょうか。
学校側としては大変だけど……(ペッピーノ)
青森県で中学校教師をしています。学校を公開することで、教師の仕事は、はっきり言って、増えます。いろんなこと(きちんとした意見でない地域や父兄の口出し……)も予測されますが、でも学校がこれから生き残っていくためには、公開していくしかないでしょう。
心を開いてくれた「笑顔とお手紙」(stardust)
小学校の前を通った時に、中から出てきた一年生位の女の子が、恥かしそうにニコニコしながら挨拶をしてくれました。わたしは反射的に返事はしたものの、戸惑いを感じてしまいました。あまりにもかわいい笑顔だったので、面食らったのかもしれません。しばらくして、あッそうだ! 手紙だ! と気が付きました。数日前に、その小学校のから「地域のみなさんへ」という生徒が書いたお手紙が届いていたのです。「みんなで挨拶をしていること。危険な時は助けて下さい。わたし達を暖かく見守って下さい」という内容でした。これからは、積極的に自分から挨拶しようと心に決めました。子ども達の純粋で、くったくのない笑顔や笑い声が、どれだけ大人たちの心を和ましてくれていることでしょう。こういうちょっとした触れ合いを積み重ねることで、少しずつ着実に、開かれた理想的な学校に近づけることが出来るのではないでしょうか。
みんなで子育て(和歌乃・岡山・未婚・31歳)
家族や教師だけで無く、みんなで子育てをする事が必要な時期に来ていると思います。学校を学校独特の決まりのみで、運営して行く危険性が、現在多く問題化されているような気がするので、ぜひ開かれたものにしていくべきだと思います。今回の事件は大変残念ですが、開かれたから起きたのでしょうか?!閉鎖的な社会の鬱屈が起こした事件、とも言えるのでは無いでしょうか。差別、偏見が人の心を当り前に傷付けて、精神障害者が立ち直る機会も得られないとも聞きますし……。何が今大事なのか、よぉく見極める必要があると思います。
「学校」は閉じすぎている(ひろまま)
今の日本の学校は、閉じすぎだと思います。物理的にも情報的にも。人が集まる場所である以上、警備は必要でしょうが、凶器と強い殺意を持って、強硬に侵入しようとする、ひとりの成人男性を完全にシャットアウトするシステムは、簡単ではないですよね。閉じようとすればするほど、そういう異常な人の、こじ開けたい気持ちを刺激するような気すらします。リスクマネジメントは、学校だけでなく、常に重要な課題。危機管理しつつ、学校は開くべき! ! 誰がどんな判断で危機管理してるかすら分からないのは、一番危ないと思う。
安全性と開放度は因果関係にない(Kikumi)
「ひきこもり」「現実逃避」などの心理状態と同様、誤解が多いところだと思うのですが、閉鎖した場所のほうが開放された場所より、ずっと安全だというイメージに囚われていないでしょうか?関連性(Correlation)と因果関係(Cause-Result)の違いをしっかり認識すべきだと思います。この誤解の上に成り立つ世論は、ものすごくちぐはぐ……。それよりも開放された環境のなかでの、危機管理を徹底するほうがずっと有効です。企業のようにID導入が必要なのか、職員の増員なのか、地域の参加なのか、それらは学校のもつ特徴や地理的な要因、地域に住む人々の希望や生活様式によって異なると思います。画一化された危機管理への答えはないと思いますね。
「学校開放」とは物理的な開放ではない(kaori)
「学校開放」の狙いは、学校での子どもの教育を教師だけではなく親や地域の人たちと共に行う、ということで、校門を開けておくか閉めておくかという、物理的な問題ではないと思います。児童・生徒の安全を守るために、校門を閉める・警備員を配置するということは、これから必要となってくると思います。親や地域の人達が学校に入る時には、ある程度チェックすることも必要となると思います。その上で教師と親・地域の人達が協力して、学校教育を作り上げていく、本来のPTA活動ができればと思います。
先生にも問題ありでは?(ちびプリ)
警備を強化しても、開かれた環境は作れるのではないでしょうか?事件が起きた時のように、地域の人間が入る予定のない時には門を閉ざせばいいし、例えば週末などで使う予定がある時にはチェックすればいいのだし。それよりも、かなり個人的意見ですが、先生という人種にも問題があるような……。もちろん全員とは言いませんが、今までの学校生活を振り返り、社会人になった今、学校とういう狭い社会しか知らない先生は常識はずれな人が多いと思います。先生達がもっと色んな大人と交流するためにも、開かれた学校は必要です。ひいては子ども達のためです。

開かれるという事(まどりん)
開く、開かれる、開かれた、なんだか抽象的で、体のいい表現だと思えてしまいます。『大勢の生徒が安心してフツーに学ぶ場所』を開く対象は、新入生の子がいる家庭だけでいいとわたしは思います。広く一般に開けば開くほど、普通の考えを持たない人も入り込み易くなるのは当然でしょう。見抜けないですよ。この方は○ でこいつは×なんて……。安全を追求するなら『開く』ことは自殺行為に思えてならない。あの事件の全容が週刊誌等で公になるのを読むたびに、娘の登下校だけでなく、学校生活の時間までも安心できないなんて……。何という情けない時代なの! と嘆いています。
わたしの通っていた学校(berger)
わたしの通っていた学校は、都心にあるエスカレーター式の学校だったのですが、幼稚園も大学も同じ敷地にあるため、どこの門にもばっちり、警備員がいて、怪しい人なんか全く入らないような環境で、こんな事件が起こる余地はなかったですね。ほかの学校がどうかは知らないのですが、校門とかって普通開け放しているのですか?
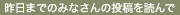
企業・官公庁がewomanリーダーズの声を求めています。一人ひとりの声をカタチにして、企業・官公庁に伝える。それがイー・ウーマンとewomanリーダーズの活動です。ぜひ登録を! 詳細と登録
詳細と登録

現在進行中のテーマはこれ! 今すぐご参加を!


 >>> 旧リーダーズ/メンバーからの移行登録について
>>> 旧リーダーズ/メンバーからの移行登録について
![]() 詳細と登録
詳細と登録