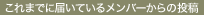

個人のモラルとは思っても(ジュディ・埼玉・40歳)
一応、育児休暇制度もあり、実際に取得して復帰し、今なお働くお母さんが何人かいます。だからまだそれができるだけましなのかもしれません。しかし、日常を見渡すと、お茶くみは女性がやるもんだ、アシスタントは女性のみなど、100%外資企業なのに旧日本式だと実感しています。しかしながら、病欠を生理休暇(有休)で取る人もいるわけで、こうなると個人のモラルの問題だとは思いますが、同じ女性として残念です。
見えない壁はまだまだ多い(yomatsu)
男女雇用均等法以来、表向きの制度としては、整備されていますし、女性の役員もいます。しかし、現場ははっきり言って古いままです。わたしが離婚のため子どもを自分の扶養に入れようとした時、「あなたの給料で子ども二人を養っていけるかどうか書いて提出しなさい」と言われました。たとえばわたしよりもはるかに収入の低い新入社員の男性が結婚したり子どもができたりして扶養家族が増える場合、そのようなことを求められるでしょうか? もちろん、答えはNOです。いまだに男性が一家の主として働いて家族を養っていくという形態が主流であり、女が世帯主として何かしようとすると、「前例がない」と言われることが多いです。見えない壁はまだまだ多いというのが実感であり、現状です。
プロジェクトを推進中(なおかよ・東京・既婚・30代)
わたしが勤めている金融機関は、女性に関するさまざまな制度は比較的充実していると思います。が、「使っていいよ! 」という雰囲気が社内にまだないというところが問題だと思っています。でも、悲観的ではありません。わたしたちが変えていくんだ! という意識でがんばっています。女性活躍推進プロジェクトもスタートしています。
少しずつ、変化が見られる(ちゃぷちゃぷ・東京・既婚・35歳)
最高2年間の育休、短縮勤務、家庭の事情による休暇制度など、大変恵まれた制度があります。が、リストラの最中、使いづらい雰囲気ですね。産休の際には「(リストラでは)能力がある人を残すより、主たる生計者を残すべきだ」と上司から退職を迫られ、復職の際に時短を申請すると「残業しないつもりなの?」と周囲は冷ややかでした。キャリアアップのために異動したくても、子持ち女性を受け入れる部署はないのです。ドラスティックに変わっている会社で、うまくキャリアを築き、周囲の理解を得る、難しいです。でも文句ばかり言うのは時間がもったいない。心がけているのはメンバーへの協力を惜しまない、自分ができることをひたすら与え続けるということ、まだわかりませんが、周囲は少しずつ変わってきているように感じています。
上司の頭の中は整備されていない(ぐーすか)
育児休暇も1歳以降の4月1日までですし、育児のための時間短縮制度も整備されています。ですが、上司(男性しかいない)の頭の中まで整備されていないので、形だけになっているのが実情です。残業の多い部署で育児休暇を取ると、「同じ職場では体も大変だし」「子どもだってかわいそうだし」などと言って、何時間も説得され続け、他の部署に転属させらた先輩も多数います。
みんな「会社で仕事を続けられるだけマシ」といって異動していきます。制度がまったくないより、はるかに恵まれていると思いますが、そもそも残業を減らそうという努力が皆無な職場では、無言の圧力があって、むしろ怖さを感じます。ちなみに子どもがいる女性で課長職になった方はいません。キャリアアップの研修は男性と同じだけ受けられるし、機会は平等であるという社の姿勢に対し、返せる言葉がないのが現実です。
第2期が担う改革(じゃらふ)
産休・育休・育児短時間……まあまあの制度は揃っていると思います。しかし、現時点で偉くなっている女性って、彼女たちが育児していたときには制度がなく、かなり苦労して両立したり、家庭はあきらめたりしてきていると思います。だから、こういう制度ができても管理職は女性も含めて利用者に対して厳しい目で見ているように感じます。制度のうえにあぐらをかいている方もいるので、厳しい目も理解できますが……。こういった周りの目を変えていくのが、われわれの担っている第2期の改革なのかな?と思います。
状況が読めていない管理職が多い(miechan)
ようやく総合職と一般職ができました。ようやく将来的に、女性管理職も推進しますといった、会社側のポーズとしか思えませんが。特に、仕事内容は大差がありません。男性にも一般職になったほうがいいんじゃありませんか?と言いたい方もいますよ。男性だけ、どんなにキャリアがなくとも、総合職から始めることができるのがいまだに不満です。性差なく、個人での評価ができる管理職を育成するのが、まずは第一歩と考えます。特にわが社には、大きく不足した部分です。女性総合職には、社長と専務が押し切って制度化してしまったようなもので、まだ、状況が読めていない管理職が多いのが実情です。
駐在期間中のルール(ローズマリー・東京・34歳)
現在の職場で女性は少数派なのですが、制度上は男女平等、結婚している女性でも希望すれば海外駐在に出たケースも非常に少ないですが、あります。かくいうわたしも結婚直後に駐在を経験しましたが、その時に「駐在中に子どもができたらどうなるのですか?」と聞いたら「即帰国してもらいます」と言われました。駐在でなければ、産休と1年間の育児休暇を取ることがごく普通という環境です。
質問をした際に、人事の見解として「文書で回答下さい」と言ったら、かたくなに「文書化はできない」と言われたのに不信感を感じました。女性の人生は一人ひとりの事情で異なるもので、制度さえ整っていればうまくいくというものではないと痛感しています。制度の徹底も必要ですが、個々の能力や条件にフレキシブルに対応してくれるような姿勢があればいいのになあと思います。望みすぎなんでしょうか? ちなみにわたしはその時、最低限の産休さえ取れれば、育児休暇なしでもベビーシッターを雇いながら駐在を続けられたらいいのに、と思っていました。

次の世代のために環境作りに努めたい(ラッキーオレンジ)
現在産休中です。育休明けたらまた職場復帰する予定です。わたしは産婦人科の医師ですが、医師の世界はやはりまだ男社会です。産婦人科医にはかなり女医が増えてきましたが、それでも結婚、出産となるとそれまでの職場を一旦退職して再就職という形をとることが多いと思います。わたしの場合も産休、育休とはいえ実際は立場上現在無職の状態です。再就職の病院は医局が探してくれるのでそういう意味では心配はないのですが、産休、育休中だけ主人の扶養に入らなければいけないし、保険手続き上大変面倒です。育休明けの女医さんは夕方5時まで、当直免除、重症患者の受け持ちは外すなど、大学病院やある程度の大きな病院(ドクターが多い)では優遇されていますが、なかなかそういう条件を出すのさえ遠慮しなければならない雰囲気です。現在医学生も女性が増え、今後女医さんも増えて結婚、出産で一時的に職場を離れなければならないことが多くなるでしょう。今はちょうど過渡期だと思います。今現在産休、育休を経験しているわたしたち世代が後輩のためにもある程度の道を作ってあげたいと思っています。道は険しいと思いますが、言うべきことは言って、環境作りに努めたいです。
建前と本音(かほり)
わたしの会社は小さく、そういう制度はありません。女性だからとか男性だからとかそういうふうに制度の中で生きてしまうと本当にやるべきことができなくなってしまわないでしょうか? わたしは各企業の常駐で仕事をしていることが多いですが、大企業ではそういう制度があるものの、ほとんど適用されていないような気がします。男性にそういう制度を意識させないといけないのに、制度を作るだけ作っておいて男性は全然理解できていないということが多いです。子どもがいる女性が外で働くということ自体に男性が理解をほとんど示していない(建前は理解しているけど本音は否定している)ようにいつも感じるのです。制度が必要とかそういう問題より男性の意識の問題だと思います。そして女性が強い意志をもって仕事をしないといけないとわたしはいつも思うのです。
自ら働きやすい環境を(edah)
やはり男性が主体であるのが現実。女性の先輩や後輩と話すと同じような状況に陥ったり悩んだり闘っていることがわかる。仕事のやり方の違いなど個人差ではなく男女差があると思う。そのようなときに、いろいろな女性の話を聞いていると自分がなぜ困難な状況に陥っているのかわかりほっとする。女性の輪があるのとないのでは大きな違いだと思う。制度だけではない部分で、女性も社内でばらばらになっているのではなく、組織だって自ら働きやすい職場環境を作っていく必要があると思う。
社風に甘んじている部分も(イスタンブール)
数年前に介護休暇・育児休暇の制度ができましたが、使ったのは1名のみです。また親会社から中高年の男性が次々出向して管理職に就くため、女性は課長以上にはなれないのが現状です。女性は使い捨てという印象ですが、社風に甘んじて責任の少ない地位に安住しているのはわたしたち自身。本当に積極的な女性は一人でも育児休暇をとって復帰しているし、もっとやりがいのある職場へ転職しているのです。
周囲の協力を得ながら女性らしく(えんちゃん)
現在の会社にはありませんが、転職前の会社では一応あり、女性の課長職の方もいらっしゃいました。他の男性課長よりも何倍も男らしい女性でした。産休、育休を利用している女性も数名ですがおり、みなさん比較的頑張っておられました。「家の近くのおいしいお店のクッキーなの」などと、おやつを配ったり、女性ならではのさりげない気遣いや努力も忘れずにされていて好感が持て、応援したい気持ちになりました。
一方、公務員の友人の話を聞くと、「制度が整っているだけに当然よ」といった態度で、あまりよろしくない話も聞きます。一部であり、すべてではないと思いますが、一方で女性の権利や地位を上げるためにがんばっている人たちもいるのに、他方では、そこに甘んじ、足を引っ張っている現実を見たような気がしました。もし、女性として見られてしまうのが仕方のないことなら、周囲の協力を得られるような女性としての仕事の仕方をしていきたいと思いました。
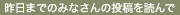
企業・官公庁がewomanリーダーズの声を求めています。一人ひとりの声をカタチにして、企業・官公庁に伝える。それがイー・ウーマンとewomanリーダーズの活動です。ぜひ登録を! 詳細と登録
詳細と登録

現在進行中のテーマはこれ! 今すぐご参加を!


 >>> 旧リーダーズ/メンバーからの移行登録について
>>> 旧リーダーズ/メンバーからの移行登録について
![]() 詳細と登録
詳細と登録