ホーム
> news &policies > 規制改革メルマガ
> vol.2
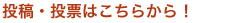
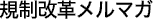
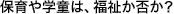
2001年7月27日(金)
今回のご意見テーマ
「保育や学童は、今後も福祉としてとらえ、進めるべきでしょうか?」
創刊号に引き続き、たくさんの投稿ありがとうございます。それぞれのご意見が、非常にポイントを明確にしていてわかりやすく、みなさんの真剣さが伝わってきます。また今回は、賛成と反対、意見が割れ、わたしも考えさせられました。 わたしの質問は、「保育=福祉」ということでイエス(賛成)か、つまり今後も「厚生労働省」にのみ「保育」を任せる、という方向を支持するのか。今後のテーマにもしていきたいのですが、わたしは、現在望まれている「保育」は、必ずしも 「福祉」だけでなく、より柔軟な考えで、選択肢豊かに提供されたらよいと思っています。
ewoman:規制改革メルマガ編集長
佐々木かをり
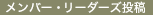

やはり保育も学童も福祉です(keroyon)
現在小学生の2人の子どもを持つ働く母親です。わたしは、今後も保育・学童を福祉としてとらえていくべきだと考えます。保育所および学童保育には大変助けられてここまでがんばってこれました。今回問題提起された大田区の指導要領の文章には、たしかにわたしも唖然といたしました。しかし、これは根本的に「福祉」という概念のとらえ方を誤っているものだと考えます。「福祉」という言葉には、ある水準の生活状態に達していない、というニュアンスが含まれるかもしれませんが、では、みんなが豊かになったら福祉は必要ないのかといったら、それは絶対にありえないことだと思うのです。わたしは、保育・学童に関連する子どもたちに対する施策については、絶対に「構造改革」や「規制緩和」の概念の中に組み込むべきものではなく、あくまで「セーフティ・ネット」としてとらえるべきものであると強く願っています。未来を担う子どもたちが、親の収入や大人の都合に左右されずに、どの子どもも健全にすこやかに育っていく環境を整備することは、明らかに立派な「福祉」の概念です。
福祉とは何か(Dulcian)
「『福祉』という言葉には、ある水準の生活状態に達していない、というニュアンスが含まれるのね」という表現がありましたが、福祉を「日本の平均的生活水準に達しているかどうか」でとらえるのではなくて、非常にあいまいな言い方になりますが、「理想的な人間的生活を目指す」としてみればどうでしょう。わたしの娘も保育所に通っていますが、兄弟のいない娘にとって、毎日生活を共にする保育所の子どもたちは、兄弟に値する存在でしょうし、親以外のさまざまな大人に接することも、社会性を育てる上で大事なことだと思います。保育士は保育のプロですから、ベストをつくしている中で、親が誤った保育をしたとしても、それを補ってくれるという安心感もあります。わたしの方針として、幼児のうちから習い事をする必要はなく、人間性や社会性を育てることのほうが重要だと思っていますので、核家族では難しい点を、保育所は補ってくれる場所であってほしいと思っています。
託児所・保育所の安全基準について(mamarin)
大田区のケースのように、家庭や子どもの問題を個人の問題、プライベートな問題ととらえる行政のやり方はもう機能しません。たしかに幼稚園のように教育的な側面を求める声もあるでしょうが、現在の機構を利用するのであれば、今後、法律、保健所、医療などが協力して子どもを安全に育てていく、社会的にも守っていく、という体制を、自治体単位で進めていくのが望ましいのではないでしょうか。規制を緩和し、従来とは違う、実務的で現実的な意味での福祉としての対応が求められていると思います。
福祉は足りないものを補うもの(柚花)
福祉は、足りないものを補うもの。手を動かせなくなったときに、自分の手をあなたの手として使う。これが福祉。仕事をしたいから、子どもを見ることができない。だから、見てもらう。足りないものを補ってもらっているわけだから、福祉じゃないの? たしかに、例にあがっていた「放棄」とか「愛情不足」という言葉には理解がないと思います。だけど、幼稚園は、子どもの世話はできるけれど共同生活の学習のために通わせるのに対し、保育園は、日中、子どもを見ることができない親のための施設。保育園に幼稚園と同じような教育を望むことと、福祉ではないと思うことは別次元のような気がしました。
困っている人を助けるという意味では「福祉」だと思います(samisa1981)
経済的な理由であれ、自己都合であれ、保護者とともに過ごす時間が取れない子どもたちを、保護者に代わって面倒を見るというのであれば立派な福祉だと思います。わたしは専業主婦ですから、仕事を持つお母さんを尊敬してます。子育てだけでも大変なのに、社会に出て仕事を持つというのは本当にすごいと思います。でも子どもが淋しい思いをしているのも事実です。ですから、行政の手で保護者になり代わって、子どもを見つめてあげることは大切なことだと思います。東京都や大田区の考え方は極端すぎると思いますが、困っている人を助けるのが福祉なんですから、保育園や学童保育は立派な福祉事業だと思います。
熱があっても迎えにきてくれない……(きちゃ)
わたしは認可保育園の保育士をしています。はっきり言って保育は福祉(サービス)です。働いているお母さんは、仕事が休みの日でも子どもを預けます。遊びに行って子どものお迎えに間に合わないことも多々あります。熱があっても迎えに来てくれないし、伝染病でも医者に登園許可を無理矢理もらって預けていきます。それが現状です。そんな疲れた子どもたちを預かるのは保育園です。学童のあとも園でさらに保育しています。厚生労働省の管轄下だから、福祉はサービスという考えがあるからできるのです。長時間保育をしたり、規制を緩める。どうなるでしょう。寝に帰るだけの家庭。暖かい家庭ですか? 極論のように感じられるかもしれませんが、そういう地区もあるのです。決して狭くない範囲で……。もっとたくさん意見を出し合って、子どものための制度改革をしたいですね。わたしたちは小さな尊い命を守っていかなければならないのですから。

育児は社会の問題(stomo)
保育=福祉には絶対にNOです。うちの子どもは0歳から保育園に通っていて、保育園という社会も家庭と同じくらい重要に思っています。つい最近、病気で半月ほど保育園を休みましたが、保育園に久々に行ったところ、驚くほど元気を回復しました。
「家庭が一番」というのは、大人が考えた事で、子どもはもっと社会的なんだということを認識させられました。保育園のいいところは、早くから社会の一員としての自覚を持つことだと思います。それを考えても「家庭で足りない部分を補う」という発想では、保育の在り方を誤ってしまうと思います。子どもは大人よりずっと柔軟だし逞しいのです。社会全体が、子どもを保護すべき存在ではなく、社会の担い手として考えていくことが重要なのではないでしょうか。
もっと働く人たちを国は支援してください(あやとものママ)
大田区の学童保育の指導要綱を読んでとても悲しくなりました。国がそんな風に考えているとは……。わたしは二児の母親でずっと働いてきました。でも二人とも普通にのびのびと育ってくれていると信じてます。上の子は今年保育園を卒業して小学校に入学しましたが、先生たちはみんな熱意を持って指導にあたってくれたし、娘も保育園が大好きでした。下の子も元気に通っています。福祉が救済措置という意味があるなら、厚生労働省の管轄にはしてほしくないです。そういう考えではなくて、働いている人たちを支援するというふうに考えていただけたらと思います。そうするともっと働いている人に有利な保育制度、たとえば保育時間の延長だったり、待機児童をなくしたりというふうに変わっていけるのではないでしょうか? もっと働きやすい環境を作らないと日本はだめになっていくと思います
。
「福祉」の保育所からの脱皮を願っています(lb81)
保育所は「福祉」であり、フルタイムで働いて給料をたくさんもらっているのであれば、高い無認可保育所に入れるべき――これまでは、そう思っていました。そうでなければ、保育所のお迎えが18時でよいわけがありません。わたしは、ぜひ保育所をバウチャー制にしてほしいと思います。公立の保育所は数を減らし、どんどん民間が参入し、できるだけ子どもを預けてもらえるようサービスを競い合うべきです。そうすれば、自ずと18時お迎えの保育所ではなくニーズにあった時間帯で保育をしてくれるところが増えてくるはず。ただ、預かるだけではなく、幼児教育を取り入れる保育所も増えてくるのではないでしょうか? 国や地方自治体は高い保育士の給料にお金を使うのではなく、保育を必要とした人に払い(所得によって差をつけてもかまいません)、その金額が公立の保育所に使われるのか、民間の保育所に使われるのか、親に判断を委ねるべきです。
子どもを社会の共有財産として育てる(DAIDAI)
現在3才の男の子を0才から保育園に預けています。子どもができてから働き続けるのは、当然のこととして考えていました。もちろん子どもの教育費を含めたお金のためでもありますが、家庭だけでなく社会や地域、いろいろな場所にかかわっていくことで、気分の切り替えや多面的に物を考えることができると思っているからです。働く上では、長時間乳幼児を預かってくれる保育園は必須です。学童についても、近い将来の事として調べはじめたところです。学校が早く終わってしまうため、安全に友達と遊ぶ場所が必要です。子どもが安心して遊べる「場」は、親が働いているか、いないかにかかわらず、社会インフラの一部として必要だと思います。幼児虐待は、子どもと親が密室の中にいることも一つの原因です。子どもは社会共有の財産、家庭以外の「場」で過ごすことが、子どもにとっても親にとってもよい関係を築き、また子どもの社会性を育てることにつながります。子どもがもっと集中して遊んだり学んだりを安心してできるための「場」を増やしてほしい。そのためには、保育園や学童、学校にかかわる大人の数も増やし、効率でなく、質の高さを上げてほしい。税金を建物等の器でなく、運営にかかわる人件費にもっとまわすべきだと思います。
大田区の文書は全体を象徴していません(tarsh)
管轄が異なることは知っていましたが、厚生労働省で管轄される理由(定義)が「福祉」の考え方に根差したものであることは初めて理解しました。育児・教育は分けて考えるものではなく、全体を把握し、30年50年先まで育てていく事業であることは、理想として賛成のため、「保育=福祉」にはNoとしましたが、過去の経緯から二省庁に割られた事業を一つにするのは、現在の日本の構造では至難の業ですよね? これにこだわる必要はないと思います。いずれは一本化する、ただし、今ある問題を解決する速度を緩めるくらいなら、プライオリティを下げるべきだと思います。なお、タイトルにも書きましたが大田区の例はただのミスじゃないんでしょうか。縦割り下命型の役所が、あえて何らかの意図を持って廃止された文書を載せたりしないでしょう。単に連絡があったのに差し替え忘れたか、差し替えろと言うのを忘れたか、校正チェックをしなかったか、いずれにしろおそまつな話ですが、そんなこと、誰にでもあるさと考えて、中身をチェックするのが重要だと思います。
反対です(セプテンバー・ソング)
子どもにとっても当然、その子一人ひとりに人格・個性があるのですから、「福祉」とは少々かけ離れるのでは? 国の予算の関係などで「福祉」枠でとらえるのでしょうか。その辺の施策的なところはわたしにはわかりませんが・・・。それにしても、大田区の話には正直参りました。この平成の世の中になって、それはないのではないのでしょうか。役所でも熱心な方もいらっしゃるとは思いますが、「前例にならって」だとかで、なかなか新しい方法を取り入れることは難しいのでしょうか。 たしかに役人になれば、民間企業のように、ちょっとしたことではリストラされない、そういった「危機感」を持つことが無理なのかもしれませんが、ごく当たりまえに税金を納めているわたしには、こうした将来性のある人材育成のためにも「人」に投資するという考えで、保育・教育のことを考えてもらいたい。
意識を変えて、みんなで子どもたちを育てていくべき(どろまり)
保育・学童は(幼稚園もそうだけど)、教育と福祉ではくくれないものだと思う。これまで、3人の子どもを幼稚園、保育園、学童保育所(そのころは、わが地域にはなくて自分たちで作った)に預けて、ずっと仕事をしてきました。ある時こういうことがありました。「子どもが熱を出したので迎えに来てほしい」という連絡が会社に入りました。「わたしは行かれないので、夫に連絡をして代わりに行ってもらう」と言ったら、子どもが夜「ママ、先生がひどいママだね、って言ってたよ」と言うのです。熱の出た子どもを迎えに来ない母親なんて、ということを、保母が、子どものいるところで話をしていたらしいのです。園長先生に抗議をし、先生たちも非を認め謝ってくれましたが、保育に携わっている人たちでさえこんな状況でした。「保育園に預ける=子どもはかわいそう」という周りの意識はあまり変わってないのでは。子どもたちが育っていく地域の中で、預ける場所が選択でき、費用もかからない、というのが理想ですし、これからの社会はそうあるべきなのではないでしょうか。
反対! 保育・学童は福祉に非ず(けこ)
メルマガにもあったとおり、福祉は、何らかの理由で不足する生活に対するサポートであるはず。福祉という言葉の影におかれている限り、自発的に働きたい人(男性も含む)たちの満足のいく制度はできないと思うし、すでに現実とも乖離しているはず。保育・学童は福祉ではなく、それを利用するのに困難な状況にある人たちが受ける部分を、福祉としてサポートするべきではないでしょうか? そのためには縦割り行政が改善されないと難しいでしょうね。
たしかに福祉なのかもしれないけれど……(オラシオン)
でもやっぱり「NO」です。双子の息子は、来年3年保育で幼稚園に入れる予定でした。経済的な理由もあって、自分の持っている資格を活かして働きたいので、できれば延長保育をしてくれる幼稚園を探していました。なぜ保育園をはじめから考えなかったか・・・。まずは、これから仕事を探すとなると、なかなか認可の保育園に入りにくい(すでに働いているママが優先される)、そして、幼稚園に比べるとやはり内容が保育に留まってしまうから(行事も少なければ、楽器を使ったり、物を作ったりする機会が少なかったり・・・)。でも、保育園と幼稚園とを分けるのは、これからはおかしいような気がします。幼稚園だって延長保育をしているところもあるわけだし・・・。幼稚園並みのことを、すべての保育園に望むのはおかしいけれど、保育園にもいろんな保育園があっていいんだし、そのためには、「保育=福祉」という考え方から脱しなければ、ありえないわけなんですよね。幼稚園に延長保育が導入されるように、保育園にも教育を盛り込むことはおかしくないと思う。幼稚園と保育園の中間みたいなものが、もっとあってもいいのかもしれないと思います。
|

|
|


 >>> 旧リーダーズ/メンバーからの移行登録について
>>> 旧リーダーズ/メンバーからの移行登録について